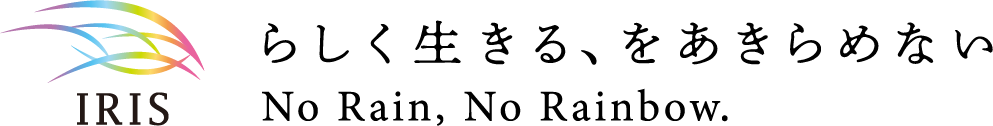以前、『同性パートナーでも使える住宅ローンについて記事』で解説しました。
まだまだ日本の法律では同性パートナーが婚姻関係を結ぶことはできませんが、一部銀行が実施している「同性パートナー向け住宅ローン」を利用することで、二人名義の住宅を購入することができるようになりました。しかし、そのようなローンを利用して住宅を購入しても、「住み始めたから一安心!」と気を緩めることはできません。
家もローンも、これから数十年にわたって付き合っていかねばならない存在です。そして、それらは相続される「財産」でもあり、課題は2人の間だけにとどまりません。今回はLGBTsと相続について解説していきます。
同性パートナーによる住宅購入では相続に関する手続きが重要
「すべての人は死すべきものである—―」
論理学の教科書で”万物の真理”として紹介される文章です。あなたにとってどんなに大事な人でも、そしてあなた自身も、いずれ訪れる死から逃れることはできないのです。そして、残された人には相続という問題がついて回ります。
相続とは、ある人が死亡したとき、他の人に権利や義務が移動することをいいます。一般的には、親が亡くなったとき、子に財産や借金が引き継がれることを想像されるのではないでしょうか。日本の法律では、自分の死後、自分の財産を誰に渡すか決めることができますが、何もしなければ民法であらかじめ決められている人に相続されます。
法律で相続できることが決まっている人を「法定相続人」といいます。そして、同性パートナーは原則として「法定相続人」にはなりません。つまり何もしなければ、せっかく二人で住宅ローンを組んで買った家なのに、他の人のものになってしまうかもしれないのです。だから、同性パートナーの住宅購入では相続手続きが重要といえます。
同性パートナーに財産を遺す方法
まずは、同性パートナーに財産を遺す方法について解説します。
”遺贈”という方法
法定相続人の対象となりうるのは、「配偶者」「子供(直系卑属)」「実の親(直系尊属)」「実の兄弟姉妹」です。「配偶者」とは法律的に婚姻した人のことを指すので、(仮に裁判所に内縁関係が認められても)婚姻関係にない人は法定相続人にはなりません。

より細かく言えば、法定相続人は代襲相続(子供が亡くなっていたら孫に相続権が引き継がれること)や相続欠格(相続人としての資格を失うこと)によって、範囲が広がったり変わったりします。しかし、何の法的関係も結んでいない同性パートナーの場合、「配偶者」以外の法定相続人にも原則当てはまることはありません。
では、同性パートナーに財産を残すことはできないのでしょうか。それを解決するのが遺贈という方法です。
”遺贈”するために遺言を書く

自分が死んだとき、誰かに無償で財産を渡すことを「遺贈(いぞう)する」といいます。相続と何が違うの?という疑問もあるかと思いますが、ここでは法定相続人以外に財産を渡すことをそう呼んでいると思っていただければ間違いありません。
あなたが亡くなったとき、自分の意思によって、遺贈する相手と財産を指定することができます。しかし、自分の意思といっても、死んでからでは「大切なパートナーに住宅を遺贈したい!」と伝えられません。また、生前周囲にそう話していたとしても基本的には無効となります。(危急時遺言を除く)
これまた決められた方法で意思を伝えなければならず、その書面を遺言(いごん)といいます。
※法律用語としての遺言は「いごん」と読みます。
遺言の書き方にはルールが細かく決められており、ルールに従っていない遺言は無効とされることが非常によくあります。(遺言の具体的な書き方や、遺贈の種類などはまた別の機会に解説したいと思います。)
住宅のように指定方法が複雑な財産については、公証役場というところで作成してもらえる「公正証書遺言」が最も確実です。
公証役場という機関では、公証人と呼ばれる人が、法律の規定通りに「公正証書」として有効な書類を作成してくれます。
養子縁組・性別の取扱い変更という方法も
また、少し特殊な方法ですが、同性パートナーを法定相続人にしてしまうという方法もあります。
それが養子縁組と、性別の取扱い変更という方法です。
養子縁組は、年下のパートナーが年上のパートナーの戸籍上の子供になるという方法です。市区町村の役場に届け出ることで、比較的簡単に手続きできますが、パートナーは本来親子ではないので、少々複雑な関係となります。
相続の問題は多少解消しますが、両者が話し合って、十分納得したうえで行うべきでしょう。性別の取扱い変更は、一部のトランスジェンダーの方には有効な手段となりえます。これは一定の要件を満たし、裁判所に申し立てれば、自分の戸籍上の性別を変更することができる制度です。
パートナーと戸籍上異性となれば婚姻できるので、配偶者として法定相続人となることができるのです。しかし、性別の取扱い変更には性適合手術を受ける必要があるなど、非常に身体的負担の大きい要件を課しているため、気軽に行えるものではありません。
すべての財産を渡せるわけではない?
さて、ここまで遺言の手続きについて解説してきました。「面倒な手続きを経たらもう安心!」かと思いきや、そうではありません。
相続には、法律でどうやっても変えられない決まり(強行規定)があるからです。民法では、一部の法定相続人に「最低限これだけは相続したいと主張できるよ」という権利を認めています。その権利を法定相続人の「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。
法定相続人の遺留分
遺留分は、法定相続人であれば誰にでも認められている権利というわけではありません。そもそもこの権利は「遺された人が生活に困らないよう配慮し、今まで一緒に稼いできた人に報いるためのもの」だからです。
具体的には、配偶者と子供(直系卑属)に認められていて、そのいずれもいない場合には親(直系尊属)に認められる権利です。そして、遺留分として保護されうるのは全財産のうち、最大で「半分(2分の1)」となっています。より現実的な問題として考えたとき、同性パートナーが遺留分を請求されるケースは、主に以下の2パターンになると思われます。
1.亡くなったパートナーに子供がいる場合
2.亡くなったパートナーに子供はいないが、親が存命である場合
もちろん、そのほかのケースもありえますが、ここでは上記の場合で考えます。亡くなったパートナーに子供がいる場合、もともとストレートだった方や、何らかの理由により子供や孫がいる場合が考えられます。このとき、子供(直系卑属)の遺留分は「半分(2分の1)」となります。なので、パートナーに対して全財産のうち「半分(2分の1)」までは、自由に遺贈することができます。
亡くなったパートナーに子供はいないが、親が存命である場合、親、もしくは祖父母のみが存命であるというケースも考えられます。この場合、親(直系尊属)には「3分の1」の遺留分があります。なので、パートナーに対して全財産のうち「3分の2」まで残すことが可能です。
遺留分は放棄してもらうことができる
遺留分はあくまで法定相続人に認められた権利であり、法定相続人にとっては必ず行使しなければならない義務ではありません。たとえば、親がパートナーとの関係を十分理解していて、配偶者と同等の立場だと思っているのであれば、遺留分の放棄を行ってもらうことができます。しかし、現実問題、実の子が亡くなった後、法的な拘束力のない他人に、どれだけ配慮してくれるかは不明です。
そのため、本来であれば、生きている間に放棄してもらうことが望ましいのですが、家庭裁判所の許可が必要という大きな障壁があります。そもそも大切な人の死など考えたくもないことですし、親の立場からしてみたら「そこまで信用されていないのだろうか?」と感じてしまう可能性も否定できません。
同性パートナーにとって、法定相続人に遺留分を放棄してもらうことはなかなか難しい問題のようです。
税制上の対策
また、同性パートナー間で財産を遺贈した場合は税制上の優遇を受けられないという問題があります。
一部の法定相続人に認められる優遇が、同性パートナーにはないのです。どのように違うのでしょうか。
同性パートナーの相続税の基本
まず、相続税の原則について確認しましょう。相続税は、相続する財産の総額によって税率が変わる累進課税となっています。最初に「法定相続人によって相続された場合の控除を適用」した金額で計算し、最後に「遺贈された人に2割増しの税金を課す」という形をとります。(ややこしいですね)
一方で、基礎控除は同性パートナーであっても適用となりますので、仮に法定相続人が0でも3,000万円までは課税はされません。課税率は以下のようになっています。
|
課税価格 |
税率 |
控除額 |
|
1,000万円以下 |
10% |
|
|
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
|
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
|
1億円以下 |
30% |
700万円 |
|
2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
|
3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
|
6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
|
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
パートナーの遺した財産が5,000万円で、包括的にすべてを遺贈したと仮定しましょう。法定相続人はおらず、すべて遺されたパートナーに財産が遺贈されたとします。
・5,000万円 – 基礎控除3,000万円 = 2,000万円
が、遺贈の総額です。これに上記税率を掛けます。
・2,000万円 × 15% – 50万円 = 250万円
さらに、「2割加算」をします。
・250万円 × 1.2倍 = 300万円
これが同性パートナーにかかる相続税になります。
同性パートナーはあらゆる控除の適用外となる
では、これが同性パートナーではなく「配偶者」だった場合はどうなのでしょうか。実は配偶者に対しては1億6,000万円までは非課税となる配偶者控除が適用となります。上記のケースに当てはめるとどうなるか、ゼロです。かなり不公平感が出てきますし、5,000万円の財産がすべて住宅だった場合、いきなり300万円もの支払いに迫られることになります。
住宅を手放すことを検討しないといけない事態に発展しかねません。
住宅の遺贈では不動産取得税も
また、住宅の相続の場合、気にしなければならないのは相続税に留まりません。法定相続人以外が不動産を遺贈された場合、高額な不動産取得税と登録免許税が課せられます。住宅の場合、不動産取得税が3%、登録免許税が2%の合計5%となっています。
現在は一部軽減税率が適用されていたり、包括遺贈の場合は不動産取得税がかからなかったりするので、単純に不動産評価額に5%を掛けた金額が課税されるわけではありません。しかし、法定相続人であれば0.4%で済むところ、同性パートナーでは非常に大きな負担となります。
パートナーシップ制度を利用して相続はできないのか?
パートナーシップ制度はあくまで自治体の制度で、法律とは無関係なものです。パートナーシップ制度の恩恵が受けられるのは、パートナーシップ制度を利用している自治体内のみです。パートナーシップ制度を利用したとしても、婚姻のように2人の関係を国が法的に承認するわけではありません。例えば2022年11月から制度運用が開始された「東京都パートナーシップ宣誓制度」の解説ページには、以下のように記載されています。
「法律行為である婚姻とは異なり、パートナーシップの宣誓により法律上の効果を生じさせるものではありませんが、都は、本制度の導入も1つのきっかけとして、多様な性への理解が深まり、誰もが自分らしく生き生きと活躍できる社会となることが大切であると考えています。」
そのため、パートナーシップを結んだうちの一方が突然亡くなったり、意思表示ができない事態になった場合、先述した遺言などの対策を取っていないと、法的な効力をもつ遺族に全財産が奪われてしまったり、住居や店舗を奪われかねません。こうした聞くに堪えない悲しい話は、残念ながら実際に起きています。
LGBTsの住宅購入はご相談を
このように、LGBTsの住宅購入では、ストレートの夫婦が考えるよりも多くのことを対策しなければなりません。生命保険の準備や預貯金の計画などで、プランニングできるケースもあります。
同性パートナーの住宅購入はぜひ弊社にご相談ください。